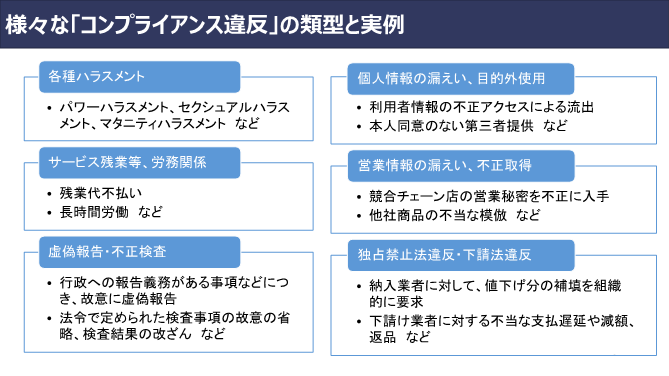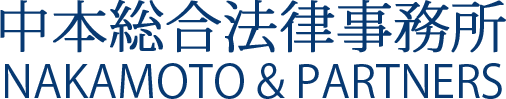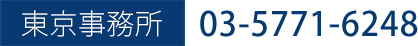企業活動における「コンプライアンス」の基本
弁護士 大髙 友一
1 はじめに
おそらく、「コンプライアンス」という言葉をこれまでに一度も耳にしたことのない方はいらっしゃらないでしょう。「コンプライアンス違反があった」とか「コンプライアンスの観点から問題」といったフレーズは、ニュースなどでもよく聞かれるところです。それだけでなく、数年前に大きな話題となった中古車販売・買取会社の不正請求や芸能プロダクションの創業者による不祥事をあげるまでもなく、「コンプライアンス」に問題があるとされた企業は、社会的信用を失い、企業存続さえも危うくなってしまうことがある、そういう時代になっているということも、今さら言うまでもありません。
しかし、「コンプライアンス」の意味を正確に理解されている方は、案外少ないのではないでしょうか。本稿では、「コンプライアンス」の基本的な考え方を明らかにした上で、企業が「コンプライアンス」を重視した組織であるために必要と思われる処方箋をいくつか簡単にご紹介したいと思います。
2「コンプライアンス」とは何か
「コンプライアンス」という言葉、日本語では一般に「法令遵守」と訳されています。しかし、「コンプライアンス」の元になった英語の「comply」の意味は、「ルールや指示等に従って行動する」ということです。ですから、「従うべき対象」は「法令」だけに限られません。企業活動をする上で関係する社会規範(=常識)や企業自身が定めた理念・ビジョン、自主ルールなども「コンプライアンス」の対象に含まれます。
要するに、企業活動における「コンプライアンス」とは、社会から求められるルールをきちんと守って、ビジネスをしなさいということです。なんだ、当たり前のことじゃないか、と思われるかもしれせん。では、なぜ、こんな当たり前のことを、わざわざ「コンプライアンス」として強調するようになったのでしょうか。
一つには、企業としての社会的責任があります。「経営の神様」と称される松下幸之助氏は、「企業は社会の公器である」と述べられました。まさしく企業も社会的存在の一つですから、利益を上げるためであれば何をやってもよいということではなく、社会で求められるルールをきちんと守ってビジネスをしなければ社会から受け入れてもらえない、ということです。
もう一つは、一般市民の意識の向上やインターネットなどメディアの進化による社会の目の変化があるでしょう。「ネット炎上」という言葉もあるように、「コンプライアンス」違反が発覚したときの企業の社会的信用の喪失の大きさは、「コンプライアンス」違反によるマイナス情報が長くネット上に残ることなども含めて、昔とは比べものになりません。
3「コンプライアンス」を重視する組織であるための処方箋
このように、現代は、「コンプライアンス」の考え方が欠如した企業は信頼ができない、安心して取引ができないとみなされる時代です。だとすれば、「コンプライアンス」を自分たちの企業活動を縛るものではなく、企業活動の前提となる行動規範だと積極的に捉えることが必要となります。つまり、「コンプライアンス」を当然のこととして動く組織であるということが求められるということです。
では、そのような「コンプライアンス」を重視する組織であるために何が必要なのか。ここではその処方箋を三つほどご紹介しておきたいと思います。
①組織の一人一人が、その考え方と行動を変えること
企業活動における「コンプライアンス」は経営層や幹部だけが意識していればよいという問題ではありません。組織の中で一人でも「コンプライアンス」意識に欠けた行動があれば、組織全体として「コンプライアンス」意識が欠けているとみられてしまうからです。
組織の一人一人が、自分自身の業務に関連する「ルール」をきちんと認識するだけでなく、常に「ルール」を踏まえて「説明がつく選択か」を考え、迷ったときには一旦立ち止まり、同僚や上司はもちろん、必要に応じて法務・経理等の専門部署、顧問弁護士や会計士等の外部専門家に相談する癖をつけることが求められます。
このように組織の意識を高めるためには、経営陣が率先して行動することに加えて、ディスカッションなどを取り入れた参加型の社内研修を定期的に行うなどの継続的な社内啓発も有益かと考えられるところです。
②「コンプライアンス」違反を迅速に察知し、回復でき
る体制を組織として持つこと
人間は必ず間違います。過失によるものも含め、「コンプライアンス」違反がいつかは必ず起きるものだと想定しておくことが、「コンプライアンス」を重視する組織であるためには必要なこととなります。すなわち、「コンプライアンス」違反が起きたときに迅速に対応し、回復できる体制を組織として持つことが、「コンプライアンス」違反が起きないようにすることと同様に重要なポイントとなります。
このような体制を構築するためには、誰かが「おかしい」と感じたら直ちに同僚や上司と情報を共有し、組織として対応できるようにすることが求められます。例えば、公益通報制度といった法律上求められている仕組みをより活用していくことも一案ですし、このような仕組みの整備と合わせて、従業員がマイナス情報であっても安心して共有しあえる風通しのよい組織を構築していくことも、「コンプライアンス」を重視する組織の構築につながっていくでしょう。
③いざ問題が起きたときには迅速かつ厳正な対応をと
ること
いくら継続的な社内啓発をしていても、また「コンプライアンス」違反を迅速に察知する体制を整えたとしても、実際に「コンプライアンス」違反事案、もしくはそのおそれがある事案が生じたときに、経営陣が甘い、適当な対応でお茶を濁してしまったとすれば、従業員は、「コンプライアンス」重視といっても所詮はその程度かと見てしまうことは必定です。まさしく、こういった会社の危機に際してこそ、会社の将来も見据え、迅速かつ厳正な対応を取ることが求められるところかといえるでしょう。